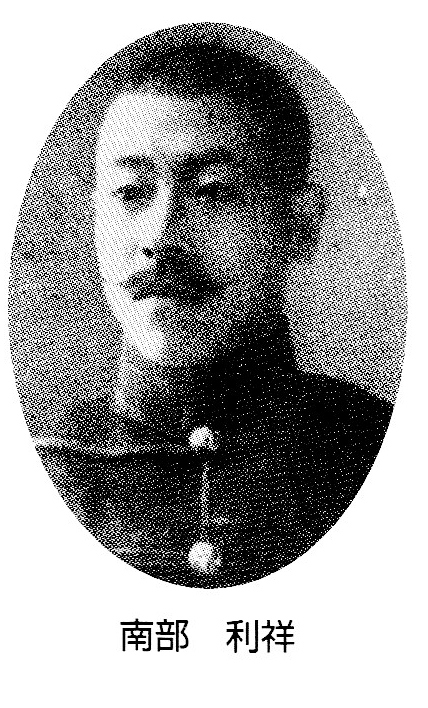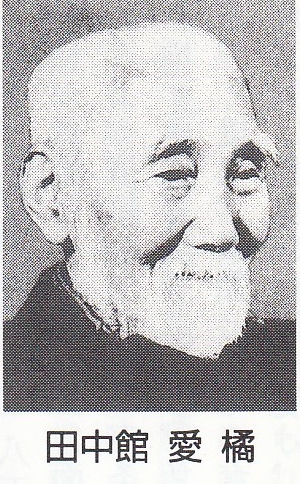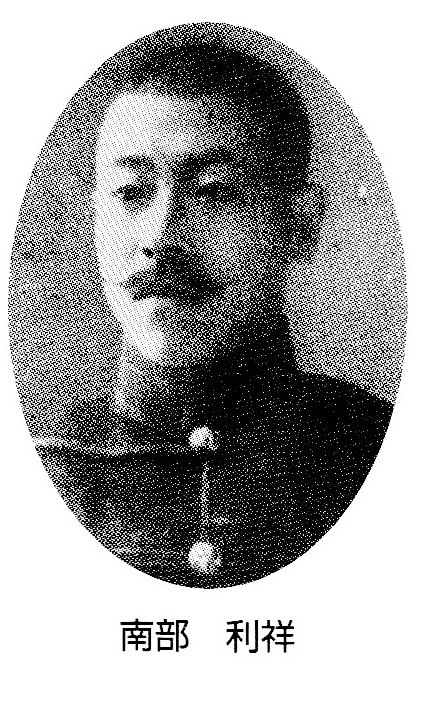「華族」と聞いて、それがどのような存在だったのか、今ではなかなかイメージすることも難しい。昭和も五十年
代生まれの筆者などからすれば、自分の生まれる遥か以前に無くなってしまったものであるから、尚更のことであ
る。
旧公家や徳川将軍家・旧大名、さらに明治以降の国家に対する勲功によって取り立てられたものなど、華族に列せ
られた家は、大正末期には952家に及んだ。華族の男性戸主には公・侯・伯・子・男の爵位が与えられ、様々な特
権を享受し、また、帝国議会における貴族院の議員となる資格を有していた(公・侯爵は25歳以上全員、伯・子・
男爵は爵別に有爵者の互選)。この制度も、日本国憲法施行により、「法の下の平等」(憲法第14条第1項)が規
定され、それに伴い華族制度が禁止された(憲法第14条第2項)ことにより廃止された。
華族やその制度、そして、その政治的・社会的な意味については、以前に比べて盛んに研究が行われている。近代
史の中において華族制度が厳然と存在し、華族が政治や社会において占めた位置が大きいために、研究上通り過ぎる
ことが出来ないからであろう。
政治家原敬と華族について採りあげた論考はすでにいくつか存在し、なかでも原が現実政治を行う上で必要だった
貴族院との交渉・提携について、様々な点が明らかにされている。今回筆者が採りあげようとするのは、そのような
側面とは異なり、原敬がこの制度そのものに抱いていた考え方や、華族の家政に深く関与していた彼の姿である。従
来の研究で明らかになった原と華族の関係とはひと味違うものをお見せできればと思う。
1 原敬の華族観
まず、この話をはじめるにあたって、原自身の華族に対する考え方、さらに華族制度についての見解はどのような
ものであったのか、明らかにしたいと思う。
いまでも「平民宰相」という首相就任当時のニックネームがついて離れない原であるが、次官・公使まで上り詰め
た官僚経験者で、その後大物政治家になった原に、「平民」ではなくなる、つまり華族となって爵位を授けられる話
がなかったはずがない。
彼にその勲功によって爵位を授ける話は生前に4回あったとされる。一度目は1922(大正3)年、政友会の首
領で原と並び称された松田正久が危篤に瀕した際(松田は男爵授爵直後死去)、二度目は2年後、大正天皇の即位礼
終了後、その大礼使長官経験者であったがために、三度目は寺内内閣において設置された臨時外交調査会委員となっ
たために、そして最後は第一次世界大戦の講和論功行賞の際である。彼は尽くせるだけの方法を尽くして、沙汰があ
る前にすべて回避したことが、『原敬日記』に詳しく記されている。
また、1921(大正10)年、原の暗殺後にも伯爵授爵の話かあったが、妻あさが受けなかったため実現しなかっ
た。その引き替えとして、「遺書」において本人が否定した位階勲等の昇叙が「恩命」を受ける形で実現した。
 |
原が華族を辞退し続けた理由については、嗣子である貢(奎一郎)が、好著『ふ だん着の原敬』(毎日新聞社、1971年)において要約している。 それによれば、 第一に、 政党首領として衆議院議員であることにこだわったこと、 第二に、 「爵位をもらった本人は、自分の功労によっていただくのだから、どうにかやって いくだろうが、二代目三代目ともなれば(初代の苫労も知らず、財産を派手に使い 果たしてしまう)バカモノも出てくるから困る」ということ、 第三に、 元老たちの選考によって決められる爵位を有り難がらなかった、 ということになる。 |
第二の理由には、華族、また華族制度というものへの原の批判的な目が潜んでいると言えよう。
さらに第三の理由の背後には、藩閥政治への原の強い抵抗心が見て取れよう。
また原は、「自分は、今の制度(筆者註 華族制度)では一家の将来の為にも、亦だ個人としても之(筆者註 華
族となること)を希望しない」、「之は、家に巨万の富を積んで豊な余財を子孫に遺すことは子孫をして暗愚ならし
むると同様であって、人は刻苦修養せしめなければ決して有為の人物は出来るものではない」と語っていたともいう
(『主張原敬一周忌記念号』復刻版、財団法人新渡戸基金、1995五年、16ページ。引用文の読点は筆者によ
る)。
こういった点から、原がその当時の華族制度そのものに批判的であり、その華族制度によって作り出された華族で
は、「刻苦修養」した「有為の人物」を形成できないという見方が拒否の原因の一つともなっていたと考えられる。
さらに、政治記者前田蓮山に漏らした言葉(『原敬伝』高山書院、1943年 所収)からは、華族になってしま
っては、その制度がもつ窮屈さから、残された子孫が迷惑してしまうという点、さらに、前出のいう、原がもってい
る「羞かみ性」といったものも理由として考えられる。
浅見雅男氏は、『華族たちの近代』 (NTT出版、1999年)のなかで、原の辞退の理由についてさらに掘り
下げた検討を加えている。しかし、原の言うことや態度は正論だとしつつも、それには「いかがわしいもの」が感じ
られるとし、原が「賊軍」盛岡藩出身であることに着目して、藩閥への憎しみの一点こそが授爵拒否の本音だとした
ことは、少々強引な立論のように思われる。なるほど浅見氏のいう点もファクターとして存在するかも知れないが、
史料を尊重すれば、本人が日記で語ったり、遺族や親しい人が証言しているような様々な理由が重ね合わさった上で
の授爵拒否とするのが自然ではないだろうか。
自身の爵位についてこのように顧みなかった原であるが、それでは華族制度そのものについてはどのような見解を
持っていたのだろうか。それを知る手掛かりは、原が大阪毎日新聞社社長時代に自身で筆を執った、華族制度につい
て論じている社説である。
 |
1898(明治31年)7月17日の社説「華族論」では、華族の体面という 側面から主張を展開する。すなわち、華族の中で資産の多い旧大名は、今のとこ ろ旧家臣達に存在する情によって体面を維持しているが、将来はそれも困難にな る。まして資産のない公家出身の華族や明治維新の功労によって華族となった人 々には、大名華族のような状況は望めない。したがって、休面を維持できないよ うな者は、華族になるべきではないし、してもいけないというのである。そし て、最後に原の真骨頂といえる論が展開される。すなわち、華族が抱く自分たち が「皇室の藩屏」であるという考え方を真っ向から否定し、国民こそがその藩屏 であると主張したのである。 |
さらに1900(明治33)年5月12日付の「授爵について」という社説においては、功労によって華族に列す
るのであれば、爵位を子孫に伝えるという制度上、華族の体面を維持するための用意をせねばならず、そのためにも
当人の死の直前や死後にではなく、なるべく生前の内に授爵するべきだと主張している。
さらに原は、華族になる資格も識見もないのに父祖の爵位を継承することは決してよいものではないと考え、もし
国家が華族制度を必要とするなら「一代華族制」を採ることを是とした(既出『主張 原敬一周忌記念号』)。
1898(明治31年)7月17日の社説「華族論」では、華族の体面という側面から主張を展開する。すなわ
ち、華族の中で資産の多い旧大名は、今のところ旧家臣達に存在する情によって体面を維持しているが、将来はそれ
も困難になる。まして資産のない公家出身の華族や明治維新の功労によって華族となった人々には、大名華族のよう
な状況は望めない。したがって、休面を維持できないような者は、華族になるべきではないし、してもいけないとい
うのである。そして、最後に原の真骨頂といえる論が展開される。すなわち、華族が抱く自分たちが「皇室の藩屏」
であるという考え方を真っ向から否定し、国民こそがその藩屏であると主張したのである。
さらに1900(明治33)年5月12日付の「授爵について」という社説においては、功労によって華族に列す
るのであれば、爵位を子孫に伝えるという制度上、華族の体面を維持するための用意をせねばならず、そのためにも
当人の死の直前や死後にではなく、なるべく生前の内に授爵するべきだと主張している。
さらに原は、華族になる資格も識見もないのに父祖の爵位を継承することは決してよいものではないと考え、もし
国家が華族制度を必要とするなら「一代華族制」を採ることを是とした(既出『主張 原敬一周忌記念号』)。
原の華族観は、華族制度の存在には消極的賛成といった立場だが、華族である要件として「体面」を保つという点
を重視し、世襲制度に批判的で「一代華族制」を志向していたと総括できよう。原がこのような華族観を有していた
背景には、当時の華族たちのあり方や、安易に爵位を与える制度の運用にかなり 厳しい見方をしていたことがある
だろう。
2 諸侯華族と旧家臣たち
前回は、原敬が華族にならなかった理由、そしてその華族観について検討を加えたが、今回は、そのような認識を
持っていた原敬が、旧主家である南部家と明治維新以降どのようなつながりを保っていたのかを見てみたい。
主立った華族には、家政機関として家令・家扶などという名称をもつ使用人(家職)が存在した。一方、旧大名家
の華族(諸侯華族)では、その家政機関とは別に、江戸時代の主従関係を利用して、旧家臣(もしくは陪臣・領民)
の出身で、政治家・実業家・軍人・高級官僚・学者など、近代社会の中で「立身出世」を遂げて有力者となった人物
を、自家の顧問や相談役(家によって名称は異なる)に起用して、家政の運営について諮問する家もあった。例え
ば、原敬の生きた時代の明治・大正期の大物たちでは、毛利公爵家(旧萩藩主家)における伊藤博文・井上馨・山県
有朋ら、島津公爵家(旧鹿児島藩主家)における松方正義・山本権兵衛・牧野仲顕ら、伊達伯爵家(旧仙台藩主家)
の斉藤実、上杉伯爵家(旧米沢藩主家)の平田東助などが挙げられよう。
|
|
原敬の政敵、加藤高明も旧尾張藩主・徳川侯爵家の旧臣として、相談人から はじまり、相談人長を経て、最後には最高顧問として侯爵家の家政に大いに関 わり、徳川家の家計を建て直し、家政改革を断行した。また、徳川家の養子 選定や分家の創立に際しても力を発揮し、結果として、徳川侯爵家は家事財政 ともに安定したとされる。(伊藤正徳編『加藤高明』下、加藤伯伝記編纂委員 会、1922年)。 旧家臣たちは、さまざまな側面において、その有する人脈や影響力を行使し て、旧主家のために尽力した。旧主家が彼らに期待したのも、自家の問題の解 決のために、彼らの持っている力を利用しようということだったと思われる。 |
前回述べたように、原は自ら加筆を執った大阪毎日新聞の社説「華族論」(1898年7月17日付)において、
旧家臣達に存在する情によって体面を維持する諸侯華族も将来はそれが困難になると警告を発しているが、そういっ
た主張の反面で、自らは旧主家である南部家の家政に深く携わり、明治から大正期にかけての南部家の動向に大きな
影響を与えていたのである。
3 藩政時代の南部家と原家
原敬と南部家の関係に入る前に、藩政時代の原家と南部家の関係を簡単に述べておきたい。話の前提として、江戸
時代の盛岡藩における家臣の家格制度を見ておこう。まず 「上々様方」と呼ばれる藩主の親族として扱いを受ける
人々、「御家門方」と呼ばれる独立して分家し、家来扱いされるようになった南部家の一門の者、主として南部家の
一族や重臣層の家柄である「高知」、勤役中藩政に功績のあった者、または高知の分家で本家から願い出のあった者
が取り立てられる家格である「御新丸御番頭」、「平士」と呼ばれる一般の藩士たちが続く。この他に領内の各地に
住居して、藩の禄を得ていた「所御給人」と呼ばれる人々も家臣団の中に組織されていた。
原家の先祖、初代平兵衛政親(?~1685)は、新参の侍を多く召し抱えた盛岡藩主南部重直(1606~
1664)に百石高で召し抱えられた。しかし、三代目の茂平慶貴(1673~1736)の代に藩内の政治抗争に
まきこまれ、家禄を没収されてしまう。慶貴はのちに帰参し、以後の当主は新田開発や献金を行うことで家禄を増加
させていく。
そして敬の祖父である七代直記芳隆(1785~1860)は藩主の側役人として功労があり、1851年(嘉永
4)10月20日に盛岡城大奥の工事について功績があったとして、それまでの平生の身分から御新丸御番頭へ格上
げになったのである(「盛岡藩国住居諸士」『岩手県誌資料・藩士(二)』所収、岩手県立図書館蔵)。そして、
1853年(嘉永6年)には加判御役(藩の出す証文に、最高意思決定機関のメンバーとして署名する家老クラスの
役)となった。明治維新段階の原家の禄高は226石8斗8升3合であった。
このように原家は幕末には上級家臣としての家格を備えていたのである。そのため、原が旧家臣として家政に関与
したのは、このような南部家とのつながりが強い主従関係の で育ったその生い立ちに規定されたためと考えて良い
のではないだろうか。